昨日、公益社団法人日本実験動物学会が、「ARRIVEガイドライン日本語版が英国3Rセンターのホームページに掲載されました。」と告知しました。
このガイドラインは、直接動物福祉について定めるものではありませんが、論文等で動物を用いた研究結果を公表する際に記載することが望ましい項目について定めており、研究計画を立て、実験結果を記録する際にも参考にする必要があるものです。
といっても日本の学術誌がどれだけ意識しているかは疑問ですが、Nature系列の学術誌など、海外では投稿規定での採用が進められており、日本の研究者もそれによって動物実験に対する意識が変わり始めていると聞きます。
■再現できない動物実験が多すぎる!
しかし、そもそもなぜ、「動物を使った研究を公表する論文にはこれを書くようにしましょう!」とガイドラインでわざわざ言わなければならないのでしょうか?
この背景には、STAP細胞論文騒動でも知られるようになった論文の再現性の低さが問題になっていることが挙げられます。
動物実験については、例えば、下記のような報告があります。
- 実験結果には誤りが多い(PLOS Medicine 2005)
- 医学生物学論文の70%に再現性がない(Nature 2013)
- バイエル社調査 2/3のプロジェクトで前臨床試験の正当性を確認できない(2011)
- アムジェン社調査 がんの主要論文89%は再現できない(2012)
ライフサイエンス分野で再現できない論文が多いのは、一つには不正がはびこっていることもあるかと推察されますが、根本的問題として、生き物を扱っているがために実験結果が一定でないことがありうるという問題を抱えた分野であることが挙げられます。
それなのにさらに、実験の際の諸条件について論文に不十分な情報しか書かれていなければ、どうやって「再現性」など担保することができるのでしょうか?
2010年にこのガイドラインが出る前には、無作為抽出した271の論文のうち、目的、使用動物匹数、動物の特徴(種、系統、性別、齢、体重等)などを記載した論文はわずか59%だといった報告がありました(NC3Rs 2009)。
また、このガイドラインが導入された後の2014年でも、使った動物の雌雄と年齢の両方を記載した論文はたった50%ほどであるという報告もありました(eLife 2016)。
そういった不完全な「研究成果」を再現しようとして結果的に多くの動物を犠牲にすることは、もはや許されない時代になってきたわけです。
「不必要な研究を最小限にすること」(日本語訳より)は、このガイドラインの目的の一つとして、明確に掲げられています。
こういったガイドラインが普及し、実験計画や情報の共有自体が改善され、動物の犠牲が減っていくことを願ってやみません。
また、論文を見てもあまりわからないことが多い、使用した麻酔薬・鎮痛薬、安楽死法についてや、飼養条件・飼育設備、福祉的配慮等についてもこのガイドラインが記載を求めていることは、特筆すべきことです。
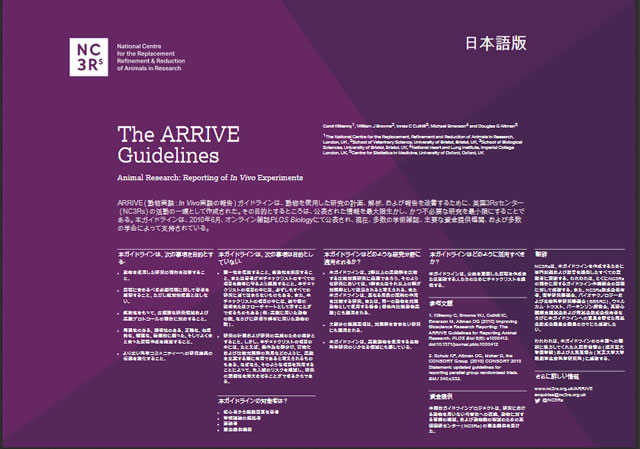
※ARRIVEは”Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments”(動物実験:生体を用いた実験の報告について)の略。
追記
このARRIVEガイドラインは、その後バージョンアップして2.0となっています。










